後景は
見ればわかると思うけど、
ロタラを中心に、ルドウィジアの類とかハイグロの類とかがいろいろ。
前景は、
グロッソ、キューバ、ニューパール、ヘアーグラス、オークロ、テネルス、ウォーターローン...なんかを混植。
混植しておくと、水槽のライフサイクルを通して優勢な種が変わっていくから、そこが面白いんじゃないかと思ってやってる。
立ち上げ当初から圧倒的に強くて前景を占めつつあるのはグロッソだけど、2週目くらいからはキューバもかなり盛り返してきている。
水草一番サンドはカリが添加されていて、他のソイルに比べると弱酸性を維持しにくいだろうと、底床の土台にはパミスにピートモスとかを混ぜたりしたのだけど(それだけの理由じゃないけど)、いろいろちょっとやりすぎたみたいで、立ち上げ時のpHは5.5(CO2添加後)。ちなみにKH 2 , GH 3。
これじゃーキューバはダメかな?とか思ってたのだけど、案の定、みるみる弱って枯れ果てそうだった。
でも、2週目以降はpHも6.5くらいで落ち着いて、そのあたりからキューバが盛り返してきた。追加で石を入れたりもしているし。
いずれ、ソイルが泥化してくるような時にはヘアーグラスが(今でもけっこう元気だけど)勢力持ってくるだろうし。
ほとんど全ての水草は、前の水槽からそのまま持ち込んだものだけど、唯一今回初チャレンジしているのが、ウォーターローン...ミミカキグサ。
これ、アクア関連や園芸関連のブログとかいろいろ見てると、
●最終的に慣れる水質の範囲はけっこう広そうだけど、基本的にはかなりpH低めが良さそう。
●慣れちゃえば光量やCO2はそれほど必要無さそうだけど、導入時はやっぱりこのあたりがリッチな環境のほうが定着させやすいみたい。
●慣れさせる前に、コケたり食べられたりで、導入失敗するみたい。
●いったん慣れてしまうと、ヤバイ勢いであらゆるところに増えていく
…らしい。
で、はじめてチャレンジして約3週。
導入にしくじりたくないので、深めにかなり密植。
でも、メインにはしたくはないので前景のハジの方にチョビっと植えてみました。
最初の1週間は、喰われるばかりでソイルの上に出ているところがほとんど刈り取られちゃうって感じ。
ちなみに食べているのは、エビじゃなくて、うちの場合は、ラミーノーズとかプリステラとかの魚。
美味いらしくて、もうバリバリ喰ってます。
ちなみにうちのカラシンたちは、エサの投入量が少ないせいなのか何なのか、水草をかなり食べる。ニューパールグラスの尖った先とか大好きで、食べやすい位置にあるのは、先を丸められて楕円の葉になっちゃうくらい。
2−3週目くらいからは、グロッソの下とかに這って行って小さな葉を幾つも出し始めてる。
まーいちおう成長しているので、一安心??
よく写真で見るやたらと長い葉を出されたらイヤなんだけど、あれはなんなんですかね?
光量とか密度の問題なのか?養分なのか?それとも??
このまま小さな細い葉を密生させてくれると嬉しいのだけど。





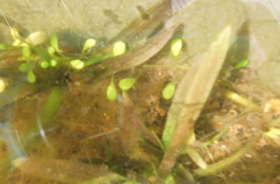 昨年の秋までにスイレン鉢に放り込んでみて、冬越しができた水草を列挙。
昨年の秋までにスイレン鉢に放り込んでみて、冬越しができた水草を列挙。